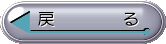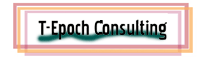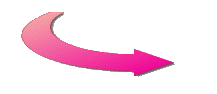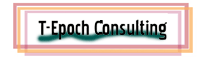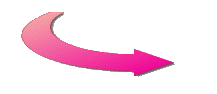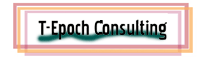 |
◆◆◆ 日々雑感 ◆◆◆ |
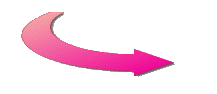 |
「日々雑感」のページでは、気に入った言葉、考え方、書籍、その他、
テーマにとらわれず、日々感じたことを思いつくままに書いていきます。
更新は2週間に一度程度を考えています。是非時々お立ち寄り下さい。
 |
今日の一言 |
-
 「考える」ということ 2005.10.11
「考える」ということ 2005.10.11 
-
ISO9001認証取得のお手伝いをしていると、必ず何らかの手順書類を作成することになります。
机上でマニュアルを書いているとどうしても自分の文章に酔ってしまい、現実から離れてしまう
こともあります。また、「良かれ」と思っていろいろ書き込むこともあります。
いつもお願いすることは、リリースする前によくシミュレーションしてくださいということです。
ちょっとした記録一つでも「この欄の意味は?」とか「ここには何を書けば良いですか?」と質問
すると答えられないケースが多々あります。あるいは記入例を作ってくださいと言っても、自分
が作成した記録フォーマットなのに、どう書いてよいかわからず立ち往生することがあります。
黙っているとそういうシミュレーションを行うことなく現場にリリースされたりしますから大変で
す。
「考える」とは何か、もう一度”考えて”みませんか(^^)
◆このページに関するご意見・ご感想はこちらまで◆
-
 「決断力」 2005.09.26
「決断力」 2005.09.26
-
今回は、天才棋士と言われる羽生善治氏の書籍の紹介です。
羽生氏は将棋の棋士ですから、当然対局などを中心にした話題で考え方や取組姿勢などを通
して決断力というものについて触れているわけですが、ビジネスにおいても頷けることが非常に
多くあり、参考になる一冊だと思います。
私は常々KKD(経験と勘と度胸)は大切であると考えており、それは個々人のスキルと深く結
びついていると考えています。科学的手法などによるデータは非常に重要で、それらが無けれ
ば仕事にあんらないことも多々ありますし、標準化などの有効性も否定はしません。
それでもしくみや制度、標準化された行動マニュアル(手順書)、データだけがあれば誰でも同
じように判断し、高いパフォーマンスを発揮できるかというと、そうではないと考えています。
やはり一人一人の経験の積み重ねと絶えざるスキル向上は大切だと、この一冊を読んで感じ
ました。
◆このページに関するご意見・ご感想はこちらまで◆
-
 「仕事を覚える」ということ 2005.09.12
「仕事を覚える」ということ 2005.09.12
-
「芸の修行というものは、天満宮様の石段を登るのと同じ事、とかかさんは言う。
緩やかな坂道を一足づつ登るように、毎日すこし上達してゆくのではなくて、平らな道が暫く続
いた挙句あるとき突然、すっと上の段に上がるようなことが多いという」
宮尾登美子氏の「陽暉楼」の一節です。
新人の頃は、与えられる仕事の範囲がごく限られたものであることもあって、なかなか全体が
見えてこなくて焦りを感じることが多いように思います。私もそうだったことをよく覚えています。
その時は、SEをしていたのですが、システム構築のいろいろな部分をいくつか行っていくうち
に、ある時ぱぁっと目の前の景色が広がるように、いろいろなことが結びついて全体像がよくわ
かるようになったことも覚えています。
「仕事を覚える」ということは「芸の修行」のようなものだと思います。焦らず、倦まず、着実に自
分のものにしていく、そういう努力が必要です。
身についた「仕事力」は「筋肉」と同じで、サボるとすぐ落ちてしまいます。取り戻すには、また
「天満宮様の石段を登る」ように時間がかかります。
新人や2年目の皆さん。なかなか仕事がわからない、できるようにならないと心配せず、焦らず、
倦まず、仕事に取組みましょう。
-
 「リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間」 2005.09.07
「リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間」 2005.09.07
-
今回は、リッツ・カールトン・ホテル日本支社長の高野登氏の書籍の紹介です。
以前マネジメントシステム・コーナーでご紹介した「システムを超えて」でも少し触れていますが、
お客様の期待を上回るサービスを実現するためには、「決定的瞬間」を大切にし、マニュアルなど
で決められたことの「その先」を考えなければいけないと思っています。
この書籍では、リッツ・カールトン・ホテルのスタッフがどのような理念を共有し、どのように行動し
ているかが書かれています。
この書籍を私がお薦めしたい一番の理由は、権限委譲(エンパワーメント)とは何かがわかるから
です。そして「理念を共有する」ということがどういうことなのかを教えてくれているからです。
リッツ・カールトンでは、スタッフが自由に考え臨機応変にお客様に対して最高のサービスを行うこ
とができるよう、権限を委譲しています。「○○をしてよい」とか「□□をする権限を与える」というこ
はエンパワーメントが広まりつつある昨今様々な企業で行われていると思います。では、リッツ・カ
ールトンでは何が違うのでしょうか。それは、リッツ・カールトンの理念に基づいてスタッフが権限を
行使し最高のサービスを実現しようとすることを、経営サイドが「しっかりサポートします」とコミットし
ていることです。しかも文書化され全員に配付されています。
経営サイドのコミットメントとサポートが無い権限委譲(エンパワーメント)は単なる「責任転嫁」で終
わってしまう可能性が高くなります。
サービス業に関係なく、「経営理念を実現するには如何にしたらよいか」、「本当の意味で権限委
譲するには何が必要か」などに興味ある方はご一読を。
きっと良いヒントが得られることと思います。
-
 「東洋のミューズ」 2005.08.30
「東洋のミューズ」 2005.08.30
-
仕事とは全く関係ありませんが、休憩を兼ねて。
奈良の秋篠寺の「伎芸天」は東洋のミューズと評されるだけあり、非常に美しい仏さまです。
ちょっと冷たくて湿った空気の堂内の薄暗がりで伎芸天を見ていると、心がとても静かになります。
この仏さまは天平時代のものですが、鎌倉時代に一部補修されているそうです。長い年月のうち
に彩色が落ち、しぶくなっていますが、作られた当初はさぞ色も鮮やかであったと思います。
秋篠寺は、秋篠宮殿下で有名になってしまい、少し騒がしいお寺になってしまった、とお寺近くの
駐車場のおじさんが当時嘆いていました。
お堂には伎芸天のほか、薬師三尊像(薬師如来、日光菩薩、月光菩薩)等仏さまがありますが、
やはり伎芸天にまさるものはないと思います。比べるものでもありませんが。
そう言えば、仏さまはたいてい伏し目がちとよく言われますが、実は違うと私は思っています。
なぜだと思いますか?仏さまの前に座って、顔を見上げて下さい。そうすればわかりますよ。ほら、
目が合ったでしょ。
-
 「プレゼンスマネジメント」 2005.08.29
「プレゼンスマネジメント」 2005.08.29
-
この書籍は、コーチ・エイ副社長の鈴木義幸氏の著作です。
「仕事は外見で決まる」という副題がついています。
ここで言う「外見」とは人間のハードウェア的なものではなく、話し方、声のトーン、しぐさ、姿勢な
ど人のあり方というか、他人との接し方などを指しています。
じっくりお付き合いしたり、よくよくお話を聞いたりすると「あぁ、なかなかよく考えているなぁ」とか
「わかっているなぁ」と思える方も、短い時間では誤解されてしまうことが多いです。
「中身で勝負だ」と思っている方も多いと思います。長い時間付き合っていかなければならない
組織のなかでならそれも「あり」かも知れませんが、それでも第一印象で誤解されると上司や部
下から信頼を得られず、思うように仕事をしていけなくかも知れません。さらにこれがビジネスの
相手であったらどうでしょう。あっと言う間に「こいつはダメだ」とか「こいつは信用ならない」と思わ
れて、取引が始まらないかも知れません。
自分のプレゼンスを磨くことは重要です。今回も自戒をこめて。
-
 コンサルティングと人材育成 2005.08.22
コンサルティングと人材育成 2005.08.22
-
私事にはなりますが、少々お付き合いを願います。
コンサルティングという仕事をしていて何にやりがいを感じるかというと、やはりプロジェクトの目
的である成果をきっちり出して、お客様に喜んでもらうことだと思います。
それは当たり前のことかもしれません。
私の場合は、もう一つあって、プロジェクトに一緒に関わったお客様側メンバの一人でもよいの
で、その人のスキルアップや意識変革のお手伝いすることにやりがいを感じます。
プロジェクトを通してコンサルタントのケイパビリティをクライアントにトランスファーすることも、コ
ンサルタントの重要な仕事だと思いますが、お客様のプロジェクト・オーナーの方から「おかげで
彼の意識が変わったよ」とか「おかげで彼はずいぶんスキル・アップしたよ」などと言っていただ
くと、やるべきことを行ったという達成感以上の喜びを感じます。
人のスキルアップや意識変革をするということは簡単にはいきません。正直なところ本当に意
識が変わったとかスキルアップしたと思える人はプロジェクトを通しても一人いるかどうかという
感じです。だからこそ、貢献できたときは喜びを感じますし、これからも一人でも多くの方々のス
キルアップや意識変革に貢献したいと考えています。
プロジェクトはコンサルタントに全てお任せで自社の要員を積極的に関わらせない場合も多々あ
ります。問題解決は最終的には自分達がやらなければならないものですから、余計なことかも
知れませんが、忙しい中でも自社要員をプロジェクトの実作業にアサインし、問題解決だけでな
く人材育成効果も狙ってみては如何でしょうか。
-
 「海馬 脳は疲れない」 2005.08.15
「海馬 脳は疲れない」 2005.08.15
-
この書籍は、脳のしくみ、記憶のしくみ、神経伝達のしくみなどを海馬の研究で薬学博士号を取
得した池谷裕二氏とコピーライターの糸井重里氏の対談形式で、分かりやすく説明していくもの
です。
その中で印象に特に印象に残ったのは「受け手がコミュニケーションを磨く」というお話でした。
「神経細胞のつながるカギを握っているのは受け手です。脳細胞がそうであるように、わたした
ちの日常でも、”受け手としての磨かれ方”が、コミュニケーションにおいて重要かもしれません。
受け手が活発であれば、関係は築かれるのです」というお話です。
よくコミュニケーションにおいて話し手の問題が指摘されます。当然、伝える側も努力をすべきで
すが、話を聞く側にも努力が必要です。極端に言えば、相手の話から何か一つでも得るものがあ
るかどうかは、受け手の心構え一つにかかっていると言っても良いと私は日頃思っており、我が
意を得たような気がしました。
脳には、「これ以上は無理」とか「これで十分」と思った瞬間からストッパーがかかってしまうそう
です。また疲れているのは目であって「脳は全く疲れない」ないんだそうです。
ですからいろいろなこと知り、考え、実践していきたいと思います。
※池谷裕二氏の著作には「進化しすぎた脳」というものもあります。こちらも是非お勧めします。
-
 一期一会 2005.08.01
一期一会 2005.08.01
-
「いちごいちえ」と読みます。皆さんもよくご存知ですね。
一瞬一瞬その瞬間が「一期一会」。もう取り返しのつかない時間。
一時顧客満足に関する活動が”流行”のように盛り上がったことがありましたが、そのときに盛
んに言われた言葉に「Moment of Truth(決定的瞬間※)」があります。
ビジネス・サイドがお客様と相対するまさにその瞬間は二度とやってきません。その一瞬一瞬
を如何に大切にし、お客様に誠実に相対するか。そう考えると、これも一期一会なのだなぁと思
いませんか。
誰かとお茶をしているその時間も「一期一会」。今こうしてこの文章を書いている瞬間も「一期
一会」。どんな時間もどんな出会いも、大切にしたいものです。
※スカンジナビア航空のヤン・カールソン氏の著書から「真実の瞬間」と訳されていますが、個人的には、
本当は「まさにそ
の瞬間」というほどの意味であると思っています。ですから勝手に「決定的瞬間」とそう考えています。悪しからず、ご了承
下さい。
-
 見通し 2005.07.22
見通し 2005.07.22
-
よく、「見通しが立たない」と言う人がいます。その人の「計画性」「主体性」が疑われます。
「見通し」は勝手に「立つ」ものでしょうか。「見通し」は立てるものだと思いませんか。
これは物事に向かうときの”気持ち”の問題かもしれません。主体的に取組んで、何とかうまく
物事を進めようとか、何とか少しでも良い成果を出そうと考えて行動している人は、安易に「見
通しが立たない」とは言わないものです。
「見通しは立てるものですよ」とは、揚げ足取りになりかねないので滅多に言いませんが、ビジ
ネスをして成果を得ようとしているからには「主体性」が必要ですし、「計画性」も大切であると
感じます。
「見通しは自ら立てるもの」、自分でも注意している言葉です。
-
 責難は成事にあらず 2005.07.05
責難は成事にあらず 2005.07.05
-
「せきなんはせいじにあらず」と読みます。
小野不由美氏作の「十二国記」シリーズ「華胥の幽夢(ゆめ)」に出てくる言葉です。
「誰かが行ったことを非難することは易しい。しかし非難するだけでは何かを成したことにはなら
ない」というような意味の言葉です。
業務プロセスの改善のコンサルティングを行っていると、ともすると「ここがいけない。これもちゃ
んとできていない」というように現状の問題点を指摘することに力を注ぎ勝ちになってしまいます。
また、例えば厳しいルールがいけないから、ルールを無くせば良いというのは問題の解決には
なりません。様々な選択肢の中から今はどうするのが良いのかを考えなくてはいけません。
現状把握は大切ですが、それを踏まえてなぜそうなっているのか(根本原因)を考え、今後どう
したら良い方向に行くのか、を考えることの方がずっと大切です。
「責難は成事にあらず」、常に心に留めている言葉です。
-
 「宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み」:日本経済新聞社 2005.06.23
「宮大工棟梁・西岡常一「口伝」の重み」:日本経済新聞社 2005.06.23
-
この書籍は、奈良の法隆寺や薬師寺の再建に携わった宮大工の棟梁のお話です。
昔かたぎの大工の棟梁の話などと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「棟梁には棟梁の仕
事がある」とか「拙速を尊ぶ」などその他いろいろ現在のプロジェクトマネジメントで言われている
ような手法のエキスが随所に現われていて、少々の驚きと確信を持って読みました。
実は非常に「科学的」なのだと。
また「口伝」の重要性や難しさは、KKD(経験と勘と度胸)は本当は重要なのだと常々思ってい
る私にとって、思いを強くする内容でもありました。
-
 七走一坐 2005.06.09
七走一坐 2005.06.09
-
「しちそういちざ」と読みます。
禅の用語で、「七回走ったら、一回坐る」というような意味だそうです。
「走る」行の後に「坐る」行を行い、自分を見つめ直せというような意味だったと記憶しています。
とにかく行動するも良し、走りながら考えるも良し。ただし、たまには(七回に一回くらいは)立ち
止まって自分の考え、行いなどを見つめ直してみよう。そういうことだと、私は勝手に思っていま
す。